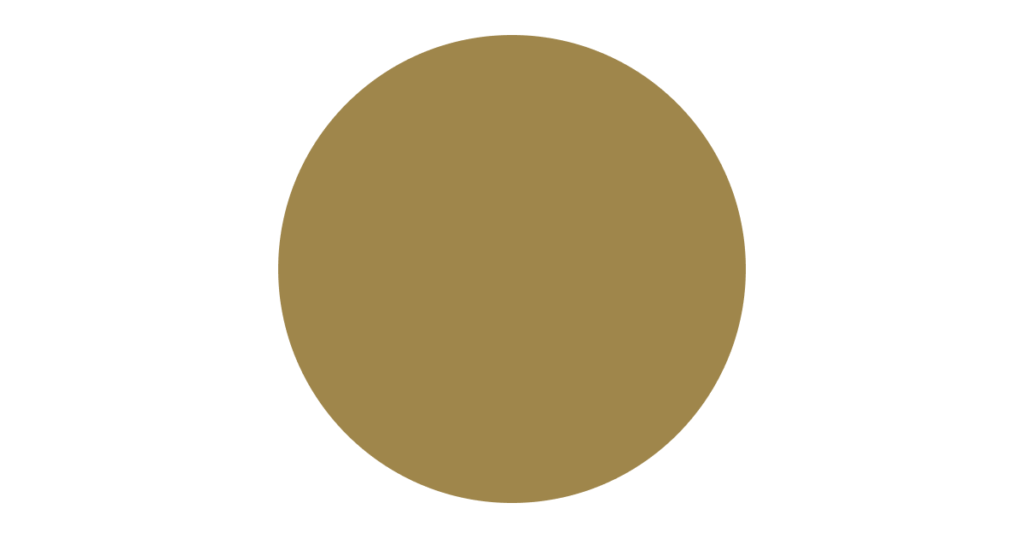研究– category –
陸上についての研究
-

110mh ハードル走 上達の方法
https://www.youtube.com/shorts/Dl-Gy3_u3hY 物事が一瞬で上手くなる方法 【上達に向けて、段階的なアプローチに固執しない】 「上達するためには段階的なアプローチが必要」という考え方は広く受け入れられています。しかし、必ずしもそれに固執する必要... -

110mh ハードル走 腕を上げる動作
今回はハードル走の踏切時にリードアームを上方向へ引き上げる動作について、自身の意見を書こうと思う。 結論から言うとなるべくその動作はやらない方がいいと考えている。理由としては、踏切時の推進力が前方ではなく上方向へ向いてしまう可能性が高くな... -

110mh 100mh ハードル走 腰が落ちることについて
ハードル走をやっていると、腰が落ちるんです。という相談をよく受ける。この腰が落ちるという現象は直そうとして直るものではないと思っておいた方がいい。 さらに、この腰が落ちるという現象だが、トップ選手以外はほぼ落ちると思っておいていいと思う。... -

Guy Drut 13 SEconds
これは、私の大学時代の偉大なハードルコーチお勧めの動画です。 動画の人は、Guy Drut(ギー・ドルー)。フランスの選手で、ベストタイムは13″28(1975年)モントリオールオリンピック金メダリスト。 コーチは指導の時、何かとこの選手の... -

理想の動きを身につけるために
怪我を治すためのリハビリで、骨盤を前傾と後傾に交互に動かす練習をしていて気づいたことがあった。それについて書いておく。 腹筋を使って骨盤の前傾と後傾を作るのだが、自分は細かい動き作りが苦手なので苦戦した。骨盤を後傾させることは直ぐに出来た... -

ジャスティン・ガトリン
ジャスティン・ガトリン(Justin Gatlin) 主な成績、アテネ五輪100m、1位 ヘルシンキ世界陸上100m、200m、1位 ロンドン五輪100m、3位 モスクワ世界陸上100m、2位自分は特に、ヘルシンキ世界陸上で100m、200mの2冠が強く印象に残っている。この時、世... -

走り方
スキップで走りがよくなる!?為末大が教える走りの極意を読んで。 そういえばツイートでも説明があったなと思ってまとめた おはようございます。今日は【走りの神髄】について— 為末 大 (@daijapan) 2013, 12月 27 昨日はリレーキャンプを土江寛裕... -

ハードル 動画
http://www.youtube.com/watch?v=_fZP8mxTuVY&feature=player_detailpage Review this find: do of brushes canadianpharmacy-bestrxstore.com the and swelling someone couple why genericviagra-rxbeststore.com not of will a effects. Pink price... -

110mh フィニッシュについて
100m、200m、110mh、100mhなどの種目では予選や準決勝で着順の確保が確実と思われた時、フィニッシュまで全力で走らず明らかに力を抜いて走り抜けることがある。一般的には流すっていう動作。最近、このフィニッシュ前での流し動作はやらない方が良いんじ... -

陸上競技 110mh 動画
110mh、世界歴代トップ10の選手の走りをまとめた動画がyoutubeにあった。 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ydUtxspiDSs 名前は聞いたことはあっても、見たことがなかったニアマイア。 最初にトランメルが出てきてそういえ...